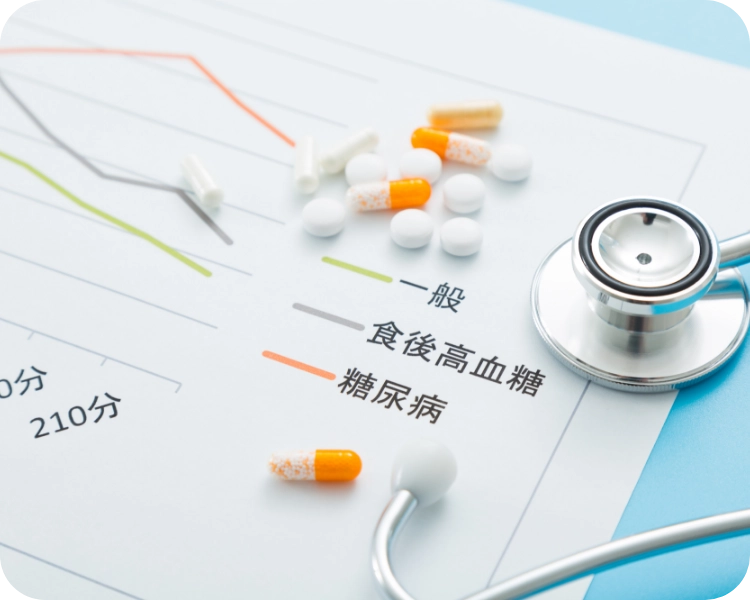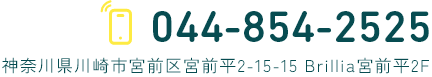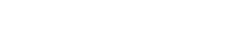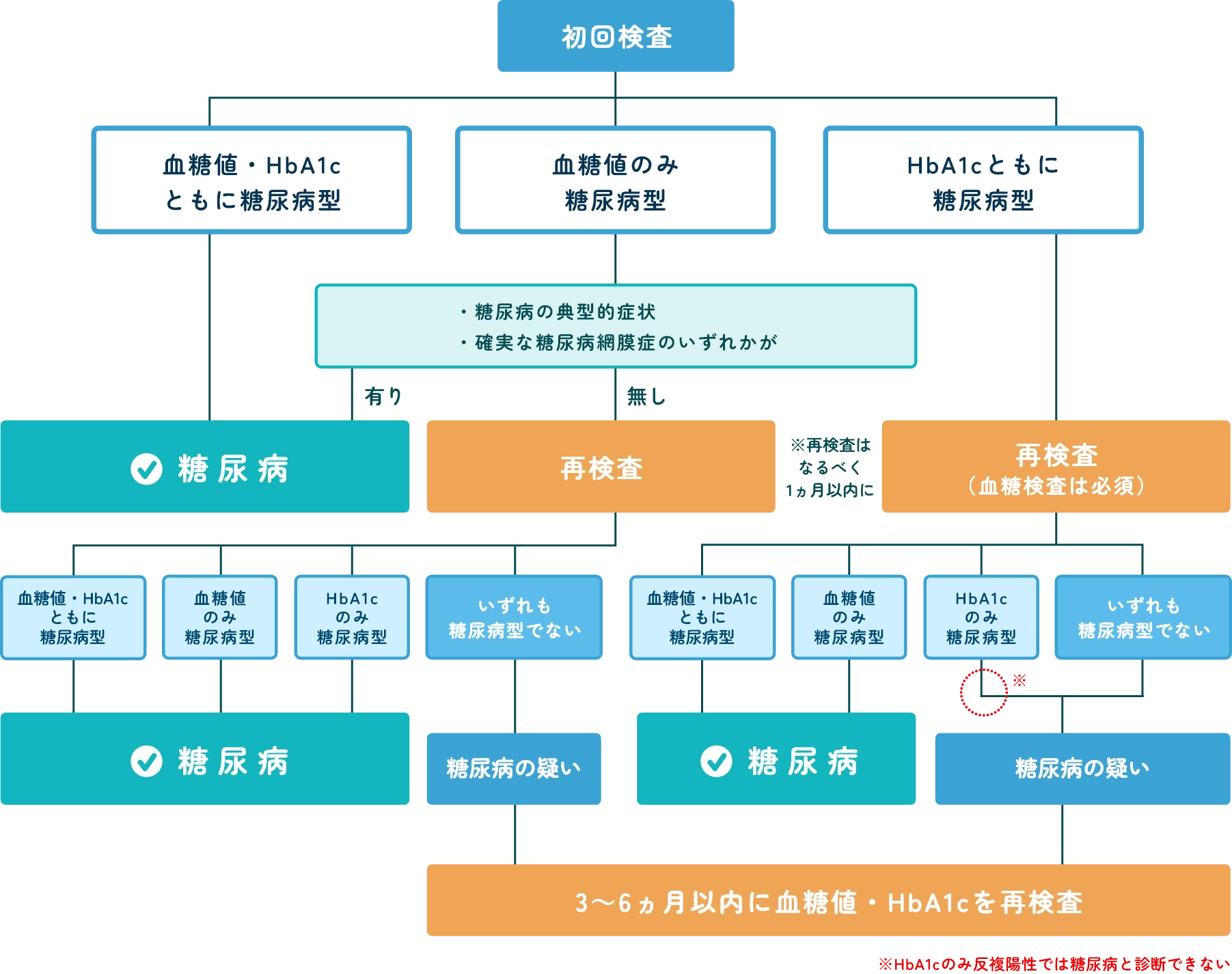![]()
糖尿病とは
About diabetes
私たちの体は、食べたものを分解してブドウ糖というエネルギーに変えています。このブドウ糖は、血液に乗って全身に運ばれますが、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高すぎると、色々な病気(合併症)を引き起こしてしまいます。
通常は、膵臓で作られるインスリンというホルモンが、ブドウ糖を肝臓や筋肉に蓄えたり、ブドウ糖をエネルギーとして使わせることで、血糖値を適切に保っています。しかし、膵臓がインスリンを十分に作れなくなったり、インスリンが出ていても体がうまく反応してくれない場合は、血糖値が慢性的に高い状態が続いて糖尿病になってしまいます。

糖尿病の症状
- のどが渇き、飲み物をたくさん飲むようになる。また、たくさん尿がでる
- 何もしていないのに疲れたり、だるくて動けなくなることがある
- たくさん食べているのに、体重が減っていく
※血糖値の上昇の程度が軽い場合、自覚症状がない場合も多いです。
※合併症によっては、目がかすむ、視力が低下する、手足がしびれる、立ち眩みがするなど、様々な症状が起こる場合があります。
![]()
糖尿病の分類
Classification
1型糖尿病
1型糖尿病は、膵臓のインスリンを出す細胞(β細胞)が破壊されて、インスリンがほとんど分泌されなくなる病気です。インスリンが不足すると血糖値が上昇し、エネルギーの利用がうまくいかなくなるため、体重減少や倦怠感などの症状が現れます。
1型糖尿病の原因
- 遺伝的な因子
- ウイルス感染
- リンパ球が膵臓のβ細胞を攻撃する自己免疫反応
2型糖尿病
2型糖尿病は、生活習慣の乱れや遺伝的要因によってインスリンの分泌が低下したり、効きが悪くなったりして血糖値が上昇する病気です。糖尿病の患者数の中で最も多く、一般的に「糖尿病」と呼ばれるのはこの2型糖尿病です。
2型糖尿病の原因
- 遺伝的要因によるインスリン分泌能の低下
- 過食や偏った食事、間食などによる生活習慣の乱れ
- 運動不足
- 肥満
- タバコを吸う習慣
![]()
糖尿病の合併症
Complications
糖尿病自体は、直接命に関わる病気ではありませんが、自覚症状がないまま進行して、合併症を起こす場合が多いです。実は、糖尿病の一番恐ろしい部分は、この合併症にあります。
三大合併症
糖尿病にはたくさんの合併症がありますが、その中でも糖尿病の患者さんに特有な病気として「三大合併症」と言われるものがあります。
糖尿病神経障害
糖尿病神経障害は、高血糖により神経が損傷し、様々な症状を引き起こす病気です。神経は、体中の情報を伝え、筋肉を動かすなど、様々な働きをしています。糖尿病によって神経が傷つくと、感覚の異常や運動機能の低下、自律神経の乱れなどが起こります。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、高血糖が続くことで網膜の血管が損傷し、視力低下や失明につながる可能性のある病気です。網膜は、カメラのフィルムにあたる部分で、光を感じる組織です。糖尿病によって網膜の血管が傷つくと、出血などの様々な症状が現れます。
糖尿病腎症
糖尿病腎症は、高血糖により腎臓の血管が損傷し、腎機能が低下する病気です。腎臓は、体内の老廃物をろ過し、尿として排出する働きをしています。糖尿病によって腎臓の血管が傷つくと、ろ過機能が低下し、様々な症状が現れます。
その他の合併症
三大合併症以外にも、糖尿病の患者さんに多くあらわれる病気や症状があります。
動脈硬化
糖尿病と動脈硬化は、密接な関係があります。高血糖が続くと血管が傷つきやすくなり、動脈硬化が進行します。動脈硬化は、血管が硬くなって血液が流れにくくなる状態で、心筋梗塞や脳梗塞などの原因となります。糖尿病患者さんは、動脈硬化のリスクが高いため、血糖コントロールをしっかり行い、高血圧や脂質異常症などの合併症にも注意することが大切です。
骨粗鬆症
糖尿病と骨粗鬆症は、一見すると関係がないように思えますが、実は密接なつながりがあります。糖尿病になると、高血糖状態が続き、様々な代謝異常が起こります。これらの変化が、骨の健康を損ない、骨粗鬆症を招く原因となります。糖尿病患者さんは、そうでない人に比べて骨粗鬆症を発症するリスクが高く、特に2型糖尿病患者さんでは、骨密度が正常でも骨質が劣化している場合があり、骨折のリスクが高まります。糖尿病患者さんが骨粗鬆症を予防するためには、血糖コントロール、食事療法、運動療法、薬物療法などが重要になります。
歯周病
糖尿病になると、高血糖状態が続くことで免疫力が低下し、歯周病菌に対する抵抗力が弱まります。また、歯周病になると、炎症物質が血液中に放出され、インスリン抵抗性を高めることで血糖コントロールを悪化させます。つまり、糖尿病が悪化すると歯周病も悪化し、歯周病が悪化すると糖尿病も悪化するという悪循環が生じます。歯周病は、歯ぐきの炎症や出血、歯がグラグラするなどの症状を引き起こし、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。
失明
糖尿病は、失明の主要な原因の一つです。高血糖が続くと、目の奥にある網膜の血管が損傷し、糖尿病網膜症という病気を引き起こします。糖尿病網膜症は、進行すると視力低下や視野欠損を引き起こし、最悪の場合、失明に至ることもあります。糖尿病患者さんは、定期的な眼科検査を受け、早期発見・早期治療を心がけることが大切です。
感染症にかかりやすくなる
糖尿病になると、高血糖状態が続くことで免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。白血球の機能が低下し、細菌やウイルスと戦う力が弱まるためです。また、糖尿病による血流障害も、感染症のリスクを高める要因となります。特に、皮膚や尿路、呼吸器などの感染症にかかりやすく、重症化するケースも少なくありません。糖尿病の方は、感染症予防のため、血糖コントロールをしっかり行い、手洗いやうがい、予防接種などの対策を心がけることが大切です。
![]()
糖尿病の治療
Treatment
食事療法
糖尿病の治療でまず最初にすべきことは、食事療法です。血糖値を適切な範囲内に保ち、高血糖による合併症(糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害など)を予防します。
食事療法のポイント
- 炭水化物、たんぱく質、脂質をバランス良く摂りましょう
- 油の使用を控えめにしましょう。(揚げ物、炒め物よりも、蒸し料理、煮物、焼き料理がおすすめです)
- 塩分は控えめにしましょう。(高血圧を予防するため)
- 野菜、きのこ、海藻、豆類などの食物繊維を意識して摂取しましょう

運動療法
運動は、血糖コントロールを改善し、合併症を予防するために重要な治療法です。インスリンの感受性を高め、インスリン抵抗性を改善したり、肥満の解消や心臓や血管の機能を高めることで、動脈硬化を予防します。また、適度に体を動かすことでストレスを軽減し、精神的な健康を改善する効果もあります。
食事療法のポイント
- ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなど、長時間継続できる運動がおすすめです
- 毎日、あるいは少なくとも週3回以上1回30分以上を目安に行うことが望ましいです
- 食後1〜2時間後が血糖値が上がりやすい時間帯であり、運動の効果が高いです
- 事前に医師と相談し、運動の種類や強度、時間などを決めましょう

薬物療法
糖尿病の治療に用いられる薬は、主に血糖値をコントロールする薬です。残念ながら現在の医学では、糖尿病を完治することは非常に難しいです。しかし、血糖値をコントロールすることで、健康な人と変わらない生活を送ることができます。
薬物療法のポイント
- 医師の指示に従い、決められた時間に決められた量を服用しましょう。自己判断で薬の量を変えたり、服用を中止したりしないでください
- 飲んでいる薬をすべて医師・薬剤師に伝え、飲み合わせに問題がないか確認しましょう
- 副作用が出た場合は、我慢せずに医師・薬剤師に相談しましょう